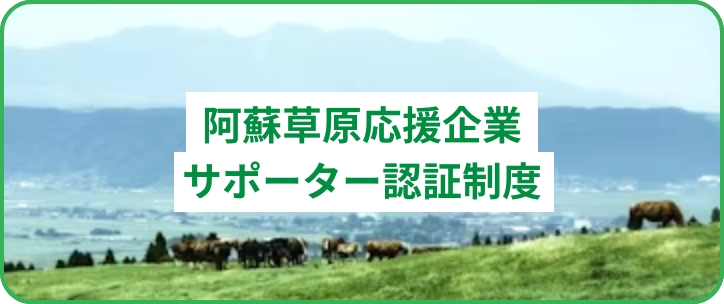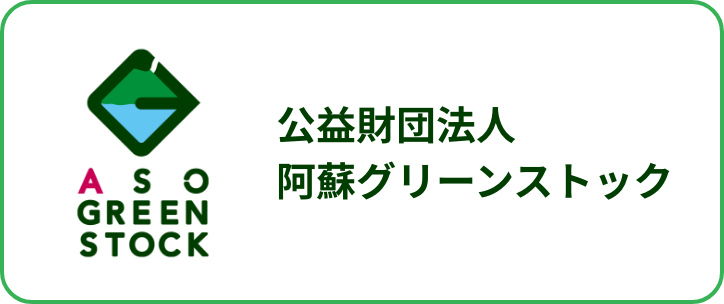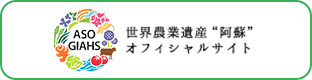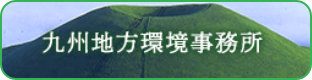カマを手に、冬枯れの草原の真ん中で茅を刈り、束ねていく千布拓生(ちぶたくお)さん。その姿は、とてもパワフル。環境調査や保全に対する専門性を持ちながら、自らの手足を動かして自然と向き合う担い手としての顔がありました。知識だけにとどまらず、自然の中で暮らしを「守り、はぐくむ」姿勢がそこにはあります。
千布さんが活動するのは、岡山県・真庭市蒜山(ひるぜん)高原。冷涼な気候と豊かな自然環境に恵まれた「大山隠岐国立公園」の一角に位置するエリア。手付かずの奥深い自然から、人が適度に手入れをすることで維持されている里山や草原、田畑まで、多様な自然と人の営みが折り重なる豊かな地域です。
大学時代からこの地域のフィールド調査を重ねてきた千布さん。鳥取大学博士課程修了後は、環境コンサルタントとして経験を積み、再び地域おこし協力隊として蒜山にIターン。専門性と実践を併せ持ちながら、この地で暮らしと自然が循環する営みの継承に力を注いでいます。
自転車で旅した経験から
環境保全の現場へ。
千布さんの原点は、佐賀県白石町。佐賀平野に広がる農地と、有明海を干拓して築かれたのどかな風景のなかで育ちました。高校卒業後は、鳥取大学農学部へ進学。
当初は、食糧危機に興味があり、農業を学ぶつもりだったそうですが、在学中に所属したサイクリング部で、日本各地を旅するなかで自然そのものに魅了されていったとか。
日本縦断の旅路で出会ったさまざまな景観。それらを“どう守るか”という視点が芽生えたのは、サドルの上でした。そこから森林生態系や植生学を学び、蒜山や大山での植物調査や、阿蘇地域でいう野焼きの作業“山焼き”にも参加をするように。大学院、博士課程へと進みながら、自然環境の調査や保全計画に関する専門性を高めていきました。
東北の自然と向き合う中で
実感した蒜山地域への想い
大学院卒業後は、環境コンサルタント会社に就職し、仙台支社に勤務。環境アセスメントの業務に携わるなかで、千布さんの中にある思いが芽生えます。
「いくら調査や研究をしても、それだけでは自然は守っていけない。保全をしていくためには、専門性を活かしつつ、さまざまな人の力をお借りしながら、いかに地域の中で、いかに実践的に保全活動を進めていくかが重要なんじゃないか」。
日本の気候では、里山や半自然草原、湿原といった自然環境は、人の手が入ってこそ保たれてきたものです。ところが、現代的なライフスタイルへの変化する中で、自然への「手入れ」が行き届かなくなった結果、植生は変わり、希少な動植物たちも姿を消しつつあります。
だからこそ、現代の価値観にあった自然資源の活用法を見出すことが必要だと、気付いた千布さん。以来、素材やサービスとして経済的な価値を生む活動そのものが、保全活動へつながるような仕組みを確立するための実践を続けています。

「資源」と「文化」が融合する
地域の暮らしを守り、はぐくむ
2021年、真庭市の地域おこし協力隊に着任した千布さん。現在も蒜山の草原や湿原を再生・保全するためのプロジェクトを実践しています。
「蒜山地域では800年以上前から、草原を維持するために山焼きが行われてきました。そこで育まれるのは、草原そのものだけでなく、草原でしか生きることのできない希少な草原性の動植物たちの存在です」と千布さん。
蒜山では、牛や馬にも草鞋(わらじ)を履かせるほど、動物も人と同じように冬を共に越す「家族のような存在」でした。雪深く厳しい季節を乗り切るための、ぬくもりのある暮らしが息づいていました。
しかし、近年は、担い手の高齢化や後継者不足で、この豊かな自然環境を維持するための山焼きも存続の危機に直面しています。それは、草原の存続だけでの問題ではなく、小さな生き物のいのちも絶滅の危機に晒されているのです。
こうした現状に危機感を抱いた真庭市は、2018年からそれまで毎年の山焼きでただ燃えてしまうのみだった草原の茅に着目し、茅葺職人の沖元さんを蒜山にお招きし、草原に生えている茅の品質を評価いただいたところ、山焼きによって通直で品質の良い茅が生えていると好評をいただきました。そこから真庭市は地域の中で茅の収穫の担い手を探し続けた結果、2020年の冬、若手農家が中心となり、「蒜山茅刈出荷組合」を結成。その中で千布さんは、収穫量の管理や注文の相談、観光客や地元の中高生などを対象とした茅刈体験会の企画・運営を担当し、茅の収穫・販売量が今後ますます増えていくように組合の活動を支えています。ここで集まった茅は、県内や中国地方を中心に、文化財建築などの保全や改修に活用されています。
近年では、「大阪・関西万博2025」のパビリオン日本館の屋根材として、蒜山地域の茅も、全国各地の茅と軒を連ね、その一翼を担いました。茅葺きの魅力を全面に押し出した日本館の設計は、自身も茅に親しむ幼少期を過ごしたという建築家の隈研吾さんです。
万博に全国の茅が集まることは、草原の火が絶えていない証。昭和の時代から、急速に減少している草原ですが、それでも確かに息づいていることを示す、誇らしい存在です。
自然と経済の間で創造する
人と自然のちょうどいい関係性
「自然を守る」と一口に言っても、それは簡単なことではありません。山焼きや草刈り、間伐などの手入れには、労力も時間を要するもの。だからこそ、「保全」と「経済」を両立させる仕組みづくりが必要です。
「自然を壊さず、でも暮らしの中で活かす。そんな“ちょうどいい関係”を目指して、蒜山の文化や暮らしの知恵を継承していきたい」と語る千布さんの活動は、地域の文化や自然を「守る」だけではなく、「生かす」ための挑戦。自然の循環の中で生み出される暮らしぶりそのものが文化の継承と言えます。

真庭市と阪急百貨店の協業ブランド「GREENable HIRUZEN」に見られるように、かつてこの地域では当たり前だった素材や知恵に、新たな価値を見出す眼が、いま蒜山地域の中で育まれています。
「今後は、茅葺き建築に使用する需要のある茅だけでなく、丈が短い・束が細いなどの理由で屋根に登ることのできない“B級品の茅”をどう生かすか。そこが今後の課題」と言います。
蒜山に眠る“未利用資源”は、茅だけでなく、湿原再生のために伐採した広葉樹も、また然り。薪や雑貨として再生する用途だけでは限界があるといいます。
「昭和30年ごろまでは、身近な自然資源として使われていたのに、いまではほとんど使わず見向きもされなくなった茅などの里山資源に、今のライフスタイルにあった新たな命を吹き込みたい」。そんな思いを胸に、自然のなかにある可能性を信じ、人と自然が支え合う暮らしを創造する営みを、千布さんは淡々と続けています。そうした歩みは、未来への希望を蒜山の風に乗せて、今日も静かに、しかし着実に、前へ進んでいます。
千布拓生(ちぶたくお)
【PROFILE】
佐賀県出身。鳥取大学農学部に進学。在学中はサイクリング部の活動を通じて日本各地の風景を見て回り、美しい景観や自然を守ることに興味を抱き、学部から博士の学位を取得するまで、一貫して、鳥取県江府町の奥大山地域の国立公園内にて、植物調査をしながら、国立公園内の自然環境の管理について研究を行う。卒業後、環境コンサルタント企業に就職し、東北地方や北海道にて、環境調査業務に従事。その後、江府町の隣の岡山県真庭市へ移住し、真庭市の地域おこし協力隊・集落支援員として、蒜山自然再生協議会の事務局を担当し、希少な環境の保全活動と、そこで手に入る未利用資源の経済化、エコツアーの企画・運営等に取り組んでいる。
[Interview]
草原ライター
中城 明日香 (なかじょうあすか)
島と草原の文化をこよなく愛する編集者・ライター。都市と田舎のどちらにも心を動かし、五感で感じたことを言葉にする。だいたいゴキゲン、好奇心だけはいつも旺盛。