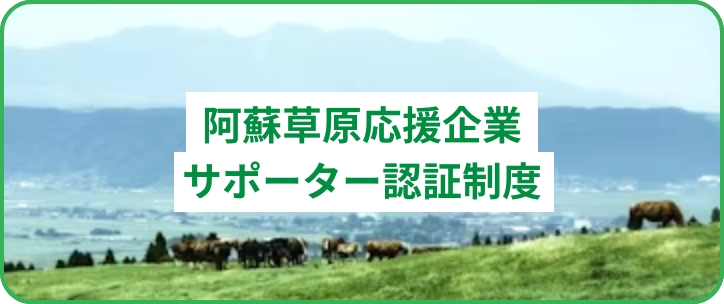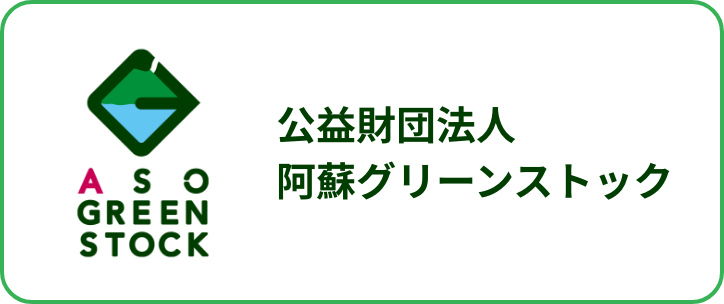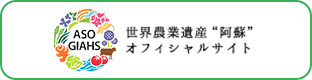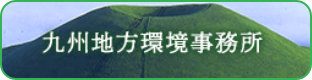草原ライターの中城です。
“草原”に出会って以来、すっかり魅了されここ数年は草原のことばかり考えています。
「草原の魅力ってなんだろう?」「人々の営みのゴールってなんだろう」
この間、私は「野焼き支援ボランティア」になり、野焼きの準備である輪地切り・輪地焼き、茅刈、野焼きという「草原」の春夏秋冬を体験し、阿蘇にいない時には、草原に関連する書籍を読み漁る日々。そんなアディクトっぷりは、自分だけのものかと思っていたけれど、いたんです。岡山県真庭市の蒜山(ひるぜん)高原のまん中に。
「株式会社阪急阪神百貨店」から、2021年から社内出向という形で岡山県真庭市の蒜山高原に暮らしている佐藤宏樹さん。ことの起こりは2020年。当時「阪急阪神百貨店」は、「小売業として収益を求めるだけでなく、CSRのように収益が伴わないものでもない、”社会性”と”事業性”が両立する持続可能な取り組みで自然環境を守りたい」という思いの元、SDGsや環境問題に関心を寄せていました。
社内で定期的に勉強会を開催し、ワンフロア丸ごと自然や環境をコンセプトにした「GREEN AGE(グリーンエイジ)」のプロジェクトが始まり、百貨店という立場から“自然共生”のライフスタイルを提案する方法を模索してきました。
そんな中、百貨店のバイヤーである前田陽一郎(まえだよういちろう)さんが、家族で蒜山高原を訪れた時のこと。1998年から約5年間、イギリスに駐在していた前田さんは、蒜山高原の風景を見てイギリスの湖水地方のような景観に感動し、「ここで日本版の“ザ・ナショナル・トラスト”のような活動ができないだろうか」と思い立ちます。
そのアイディアは、あれよあれよという間に真庭市の市長の元へと届き、「阪急阪神百貨店」と「真庭市」の協業が決定します。企業と行政が手を取り合って地域の自然や人を活かし、生かす取り組みとしてそこで生まれたのが、“人と自然のつながりのブランド化”を体現するコミュニティ・ブランド「GREENable(グリーナブル)」です。
※“ナショナルトラスト”とは産業革命で自然破壊が進んでいた英国において、豊かな自然環境や歴史的建築物の保護を目的として約130年前に設立された欧州最大の環境保護団体のこと。

「当時の真庭市は、ゆたかな自然を誇る地域の魅力を広く発信する機会と感性を欲していました。一方で阪急阪神百貨店は、真庭市と協業する以前から“サステナブル”を軸にしたフロアづくりに取り組むなど、地域の自然や文化を活かした新たな価値を持つ『商品』や『体験』を提供したいと考えていました。そんな両者の出会いは、互いのニーズと培ってきたものが見事にマッチした、まさにご縁としか言いようのないものでした」と佐藤さんは語ります。
そうした潮流の中で「阪急阪神百貨店」との共創で真庭市北部で鳥取県との県境に位置する蒜山地域で、コミュニティブランド「GREENable HIRUZEN」(以下、「GREENable」)が立ち上がりました。本格的に始動するメンバーとして、百貨店側のプレイヤーとして手を挙げた佐藤さんは、2021年に真庭市に一家で越してきて以来、真庭市の春夏秋冬の営みの中に身を置き、時に地域の住人として、時に異端の観察者として、地域の可能性を見つめてきました。
「自然共生とひと口に言っても、“ものを売る”という百貨店の立場で、そこを体現するのは、実は難しいこと。“コミュニティ・ブランド”として何ができるのだろう?と、この4年間ずっと考えてきました」と話す佐藤さん。
赴任当初は、コミュニティ・ブランドとしてどのような商品を取り扱うべきか?というところからのスタートでした。取り扱いブランドの基準を定めるとともに、オリジナル商品や、蒜山エリアでしか買えないセレクトを体現する店づくりに奔走します。そうした実績などが認められ、ブランド誕生から1年後の2022年。「阪急阪神百貨店」は、百貨店業界初となる環境省の「国立公園オフィシャルパートナー」に認定されました。


サステナブルな取り組みを身近に体感できる観光文化発信拠点施設『GREENable HIRUZEN』がオープンしたのも2021年のこと
「当初は2年の任期でしたが、実はもう4年目を迎えています。真庭市にも阪急にもかなり異例の対応をしていただいているのは理解しつつ、そんなに簡単に地域をわかった気になっては失礼だな、とも思うようになりましたし、実際に暮らしてみると、離れがたい気持ちも正直あります」。そう語る表情から、蒜山での暮らしに確かに心を動かされた佐藤さんの心持ちが伝わってきます。
「厳しい蒜山の冬は、雪かきに追われます。最初はかなり時間がかかっていたのに、そのスピードがちょっとずつ早くなる。そういう時、ここでの暮らしに馴染んできたことを感じてうれしくなります」と佐藤さん。
「そうそう、以前ね、帰宅したら家の周りの草がきれいに刈られていたことがあって。近所のお母さんが『小さい子がおって、そんなに草が生えとったらあかんやろ』って、わざわざ息子さんを呼んで草刈りをしてくれてたんです。慌てて御礼にビールを買って行ったら『いつまで御礼言うとんねん!』って逆に叱られて(笑)。なんて利他的な人たちなんやろうって感動しました」。


真庭市の木材で作ったCLTという資材を用いた、建築家の隈研吾氏が設計監修のパビリオン「風の葉」は、「GREENable」のシンボル的存在。東京・晴海に建てられたものが、“里帰り”という形で蒜山に移築されたもの
楽しむ?向き合う?
都市と地域の自然観の理解者であり続ける
生活者としてのこの場所に身を置き、蒜山へ愛着を深める一方で、百貨店の社員として、都市と地域をつなぐ媒介者として、常に“ていねいな暮らしって何だろう?”“都市と地域が共感しあえる関係性ってどんなものだろう?”と、この4年間、人知れず考え続けてきたという佐藤さん。
「GREENable活動を地域に根付かせるために出向した当初は、虫の出るアパートに悲鳴をあげていた妻も今ではすっかり慣れてしまっていますし、子どもたちものびのびと自然の中で走り回れる環境をありがたいなと思っています。蒜山での暮らしは、僕や、僕の家族にとって特別なものになりました。ここでの人々と日常をともにすることで見えてきた“ていねいな暮らし”の本質って、厳しくも優しくもある素のままの自然と“向き合う”ことなのかなと今は思っています」。
蒜山高原は豪雪地帯。2ヶ月先を見据えて暮らしの準備をする人々の暮らしぶりを、佐藤さんは「とてもきれいだし、かっこいいと感じます」と言います。
「都会では、あくまで“自然”は楽しむもの。蒜山では、“自然”は向き合うもの。両者の間にある“自然”を行き来しながら、つないでいくのが自分の役割だと思っています」。

当時2歳だった長男は5歳になり、蒜山に生まれた長女は2歳に。元気いっぱいの子どもたちも蒜山での暮らしに馴染んでいる
自身の暮らしにおける自然とのつながりは「田んぼの畔(あぜ)を歩くこと、開け放った玄関から蛍が見えること、流れ星が見えること」だとか。
一方、百貨店の社員として地域に立つ時にうれしい瞬間は「お客さまが『おしゃれ!』って言いながら、店に入って来てくださること。その瞬間に『都会に負けてないぞ!』って心の中でガッツポーズです(笑)」。
地域の方との関わり方や意識にもまた変化があったという。最初は、地元の方には「畑仕事の道具」という認識が強かった「がま細工」が「GREENable」の棚に飾られ多くの若者たちが購入したことでオシャレなアイテムとしての認識が育まれ、今では新作が完成すれば、生産者のお母さま達自らお披露目に来てくれるそう。

「地元の方が自分たちの暮らしの価値を再認識し、行動が前向きになっていること。そこに何より喜びを感じます」。
任期を延長し、蒜山に身を置き、問いを続けてきた佐藤さんが過ごした4年という“時間”そのものが、この土地の魅力を物語っています。
「流行の言葉で形容すれば、ここの人々はとにかく“利他的”。人のために動ける人たちがいる地域だからこそ、僕自身も目の前の人を少しでもよくしてあげたいと思うし、一緒に笑顔になれたらいいなと思います。これからも『GREENable』が心の通った温かい関係性を表現していける場であり続けられるならば、これ以上うれしいことはないですね」。
「コミュニティの外の人の眼が、埋もれていた地域の魅力を掘り起こす」
なんてことは地方創生の論点でもよく語られることだけど「外からの眼を持つ人」が、その地域の日常にどれくらい根差し、考え続けたか? その過程にこそ、意味があるのだと思います。
蒜山に住み暮らし、問いを続けた佐藤さんと、佐藤さんたち一家を見守ってきた蒜山の人びととの関係性そのものが“蒜山”という地域の恩恵かもしれません。「いつまで御礼を言ってるの」と言えるつながりは、どう考えたって幸福なのだから。
【PROFILE】
佐藤宏樹(さとうひろき)
大学卒業後、阪急阪神百貨店に入社。2020年からスタートした社内勉強会でSDGsや環境問題をテーマに学ぶ。共に発足した「GREEN AGE(グリーンエイジ)」のプロジェクトの一環として、2021年から4年間、社内出向という形で岡山県真庭市の蒜山高原に暮らす。阪急阪神百貨店と岡山県真庭市が共創するコミュニティブランド「GREENable 」の波及および「GREENable HIRUZEN」の運営サポートを務めた。
[Interview]
草原ライター
中城 明日香 (なかじょうあすか)
島と草原の文化をこよなく愛する編集者・ライター。都市と田舎のどちらにも心を動かし、五感で感じたことを言葉にする。だいたいゴキゲン、好奇心だけはいつも旺盛