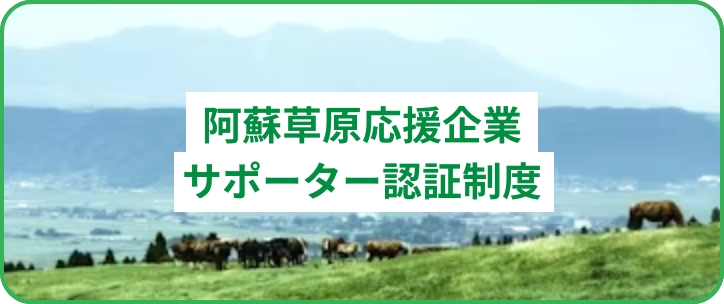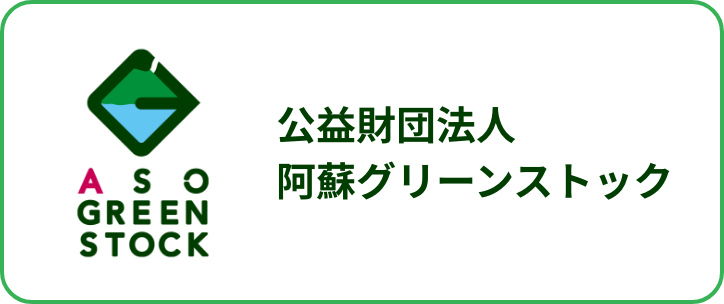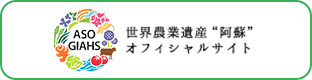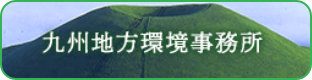“和食”と“茅葺き屋根”。一見、なんの関係もなさそうなふたつのもの。そのつながりを飄々と語るのは、「日本茅葺き協会」の代表を務める建築家の安藤邦廣(あんどうくにひろ)先生です。
聞き手は、工芸やものづくりの現場を尋ね、全国を飛び回るブランディングディレクターの行方ひさこさんです。
お話を伺ったのは、年に1度全国各地で開催される「草原フォーラム」の会場。2023年度は都内にある「東京農業大学」での開催となったことから、東京在住・第一線で活躍する行方さんに、草原ビギナーとして白羽の矢が立ちました。
和食と茅葺きのつながりとは。建築家がなぜ草原を語るのか。本当の豊かさとは。おふたりの草原をめぐる対談は、縦横無尽に展開していきます。
モダンでおしゃれ!世界に息づく茅葺き建築

安藤 「茅葺きって日本以外にもあるの?」ってよく言われるけど、オランダでは茅葺きに住むことは自慢。今の日本では個人住宅としての茅葺きはほとんど作られていないけど、茅葺きが持続しているオランダは、今の時代の風を受けたモダニズムの茅葺きができてるの。
行方(写真を見て)とてもモダンで素敵ですね!
安藤 昔は世界中に草原が広がっていて、どこにも茅葺きはあったの。茅葺きの文化を継続している世界8カ国(オランダ、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、南アフリカ、日本)が集う「世界国際茅葺き会議」を2年に1回開催しているんだよ。そこでは“茅葺き文化”をどう復活させるかを共同で考え、呼びかけているんですね。国の事情はいろいろあるから、取り組みはそれぞれのものにはなるけれど、共通する課題は必ずあります。
行方 茅葺きにも個性があって面白いですね!
安藤 茅葺きは、ちゃんとお国柄が出る。そこがいいんです。
行方 減少傾向にあるのは、維持費の高さからでしょうか。
安藤 今は確かに屋根としては1番高級になってしまったね。茅葺きというのは、茅場で刈って、束ねて、人の手で葺いて、手入れをして行くもの。人の手でしかできない手間がかかるものだから。でも、葺いたばかりの茅葺きは、黄金に輝いていて本当に綺麗だよ。
行方 そこから経年変化していくんですね。

安藤 そう。そして、いろんな微生物の宝庫になっていく。代表的なものはカビだよね。カビっていうと嫌なものと思われるかもしれないけど、チーズだって味噌だって麹だって発酵食品の元はカビだからね。
行方 なるほど。確かにそうですね。
安藤 茅葺き屋根は人が作るものだけど、元々は植物だからいろんな微生物の宝庫になっていく。黒ずんで見えるのは、いろんな微生物が食べたり、暮らした結果。人間が手を加えないと持続できない世界だけど、人間はそれをずっと繰り返して命の歴史を歩んできた。たとえ人間がいなくなって放置しても微生物は生きていけるし、茅は最終的に土に還っていく。
行方 建築資材としてはどのような特長がありますか。
安藤 人間が持つ免疫力を引き出し、香りや手触りで安らげる空間を作る茅葺きは、もはや屋根材ではなく生物環境だね。茅葺き屋根の中では、ものすごく多様な生物たちが助け合って生きている。湿度の高い日本という土地に生きる人間にとって、トータルで最善の環境が茅葺きなんだよ。今の感覚で言えば衛生的ではないという感覚があるかもしれないけど、本当の意味での“健康”は茅葺きにあると僕は思うね。
平等な建築を追求し、出会った“草原”の文化。
行方 草原に興味を持たれたのは、いつ頃なのでしょうか。
安藤 最初は“草原”には全然興味はなかったの(笑)。「茅葺き文化協会」と「草原再生ネットワーク」が一緒になって草原の未来を考え出したのは、ここ10年くらい、つい最近のことなの。茅葺き屋根の原料となる茅ってススキでしょ。山に行けばススキがたくさんあるってことはわかっていたけれど、茅となる丈夫なススキが草原文化の長い歴史の中で、人の手によって培われてきたものだということは全然知らなかった。
行方 茅葺きを通じて草原と出会われたんですね。
安藤 どちらかといえば「平和で争いのない建築を作りたい」というところから草原に行き着いたという感じ。みんなが同じものを分かち合って暮らせるような建築が僕の理想なの。草を刈って誰かに文句を言われることはないけど、木を切っても鉄を切っても大体叱られるじゃない?(笑)誰に対しても平等で、格差のない建築。そこがやっぱり1番大事かな。
行方 なるほど。草は刈っても叱られない、むしろ感謝されますよね。
安藤 民衆の建築として“茅葺き”の歴史を調べる中で、現代的な目でも評価したいし、未来につなげたいという思いから、だんだんと草原に目を向けるようになった。近代の機械的な建築とは真逆の“生物学的な建築”というものに惹かれたんだよね。
微生物と共存する茅葺きが、和食を進化させた。
行方 建築を生物学的な視点で捉える発想がとても新鮮です。
安藤 最近は腸内環境なども注目されているけど、人間も生物だから体内にいろんなものが棲みついて生きてるでしょう。建築もいろんなものが棲みついて機能することが本質的なところだと思う。そういう部分で草原に引き込まれていったというのが正直なところだね。
行方 お味噌を作ったり、パンを焼いたり。確かにここ4〜5年くらいで暮らしに発酵を取り入れる方は増えたと感じます。無機質な部屋と生物学的な空間で仕込むお味噌は、また味が違うでしょうね。
安藤 「おいしい」ということを追求すると、必ず微生物にたどり着く。茅葺きの空間で発酵を取り入れた料理をつくると1番おいしいものができると思う。味噌でもお醤油でもお酒でも、日本の和食がここまで進化したのは、茅葺きがあったからと言ってもいいと思う。和食こそ微生物の宝庫なんだよ。そうした意味でも人間の手の入った生物環境である茅葺きがもっとも豊かな多様性を生み出していると言えます。
行方 今、私たちが美味しい和食を食べられるのは、茅葺きの恩恵なのですね。だんだん“茅”というものに対する意識が変わってきました。
安藤 茅は生えてるだけで水が溜まったり、微生物が住んだり、動物の宝庫になるでしょ?茅があることによって草原が豊かになる。それは、人間が暮らす里でも同じことで、微生物が生物環境を作って、人間はそこで健やかに生きて、最終的に壊しても最高の堆肥となり土をよくする。常にプラスにしかならない。そんなものって今の世の中にはなかなか見当たらない。
行方 使うほどに価値を増していく、アップサイクルが適う素材だったんですね。
安藤 縄文時代以降、人々が稲作農業をするようになってから“草”というものが最大の恵みだということに気がついたんだよね。それを最大限に生かしたのが日本の茅葺き農業なんだよ。そういうスタイルを“作った”のではなく、持続した結果そこに行き着いた。失敗もあったと思うけど、大きな方向性として間違っていなかったから、みんなが知恵を絞っていいものだけを積み重ねていった結果だね。
行方 その一連の流れは、総称して“茅葺き農業”と呼んでもいいのでしょうか。
安藤 月日が経てば半ば腐って発酵して少し匂いもしてくる。だけどそれは、そのまま堆肥になる。しかもただ堆肥になるだけじゃなくて、土をよくするんだよ。今の農業は、化学肥料と農薬で栄養を足して収穫量自体は増えるけど、土壌そのものをよくすることは難しい。茅の場合は土の中の微生物環境を豊かにする方に働きかけて、微生物の力を最大限に引き出す。その微生物によってさらにミミズが活性化して土壌を育む。そうすると肥料や農薬も最低限で済む。だから、やっぱり日本人にとって大切なのは農業なんです。そういう暮らしに適した家を作らないといけない。
本当の豊かさは、みんなを幸せにすること。

安藤 よく“土に還る”っていうんだけど、それは“ゼロ”になるってことでしょ。人間が茅を刈って家を作る、その果てにゼロになることを「美しい」って思ってたんだけど、違うんだよ。茅はゼロどころかプラスになるんだよ。日本は島国だから必要以上にゴミを出さないとか、排水もできるだけ綺麗にしておきたいとか、道徳心かもしれないけどそういう気持ちがあるんです。建築だって壊した後に廃棄場所に困るようなものは、これからの時代はつくらないようにしなくちゃいけない。
行方 改めて“豊かさ”の意味を考えさせられます。
安藤 本当の豊かさは“見た目”じゃなくて、“みんなを幸せにする”こと。ともに生きて、誰も排除しない。そういう考え方は日本人の特質というと語弊があるけれど、私たちがもっとも大事にしてきた価値観のひとつです。自分だけが幸せで豊かになるって、割と考えやすいし達成しやすいんだよ。でも、そこで排除される人もいる。少なくともわたしはそれが嫌なんだな。みんなが幸せになることによって自分も豊かになる、っていう考えはきれいごとだと言われればそれは認めます。ただ排除することでもっと大きな不利益が自分たちに返ってくるし、想像力の欠如だと思う。
行方 まさに今私たちが目指す世界のあり方、そのものですね。
安藤 茅葺き農業の世界を一旦自分たちのなかに取り戻してみたらどうかな、ということを自分の人生の最後の仕事として残していきたい。そこで茅葺きというものは草原がなければ成り立たない。山にススキあり、海にヨシありと言われる日本人の暮らしを裏付けているのが、広大な草原・湿原なんです。古くから営んできた本当に豊かな世界を再び取り戻すことはできると思います。
行方 今日お話を伺って今すぐにでも茅葺きに住んでみたいと思いました。これまでの環境と違うので一回体調を崩してしまうかもしれませんが(笑)。とりあえず庭に一つ。お味噌を仕込めるような小さな茅葺きの空間が欲しいですね。
安藤 そうだね(笑)。腸内環境をごっそり入れ替えるっていうことだからね。でもそうすると免疫力はつくし、肌もピカピカになる。ただ、茅葺きの中でご飯を炊いて、暮らすだけでそういう体内環境が作られていくから。小さな小屋でもいいし、室内の壁に断熱材として使うという方法もある。マンションでも天井に茅を葺けば静かだし、香りも草原にいるようにいい。腸内環境も良くなる。そこでおいしい料理を食べれば楽しいし、寝室ならよく眠れるし、日常はかなり変わってくるんじゃないかな。
行方 茅葺きを今のライフスタイルに取り入れるきっかけがもっと増えてくるといいですね。今日は貴重なお話ありがとうございました。
【草原ライターのあとがき】
さて、ここまで安藤先生と行方さんが繰り広げてきた対談を紐解くと、“ノスタルジックな日本の原風景”としての茅葺きではなく、いのちあるものたちの居場所、生物環境としての物語が広がっていました。
安藤先生が茅葺きのある未来を願うのは、建築を通じて“本当のゆたかさは、みんなを幸せにすること”、という建築家としてたどり着いた答えがありました。ひとりの人間のしあわせを達成することがゆたかさではなく、みんなをしあわせにする意識を持つこと。本当の豊かさは、そんなところから生まれるのだと言います。茅葺きの文化が世界に息づいている限り、“本当のゆたかさ”を叶える可能性もまた、世界には残っているのです。
※こちらのインタビューは2024年に取材させていただいた内容をもとに編集いたしました。
【PROFILE】
安藤邦廣(あんどうくにひろ)先生
1948年宮城県生まれ。建築家。筑波大学名誉教授。日本茅葺き文化協会代表理事。里山建築研究所主宰。著書に「日本茅葺き紀行」「民家造」「住まいの伝統技術」他
行方ひさこ(なめかたひさこ)
アパレルブランドの経営、ファッション、ライフスタイルブランドのディレクターとして活動。近年では、食と工芸・地域活性などエシカル&ローカルをテーマに、昔からの循環を大切に繋げていきたいという想いから、その土地の風土や文化に色濃く影響を受けた「モノやコト」の背景やストーリーを読み解き、自分の五感で編集すべく日本各地の現場を訪れることをライフワークとしている。2021年より地域の文化と観光が共生することを目的とした文化庁文化観光推進事業支援にコーチとして携わる。国内外の工芸品やアートをキュレーションした企画展「ARTS& CRAFTS」が伊勢丹新宿店で不定期開催中。
[Interview]
草原ライター
中城 明日香 (なかじょうあすか)
島と草原の文化をこよなく愛する編集者・ライター。都市と田舎のどちらにも心を動かし、五感で感じたことを言葉にする。だいたいゴキゲン、好奇心だけはいつも旺盛