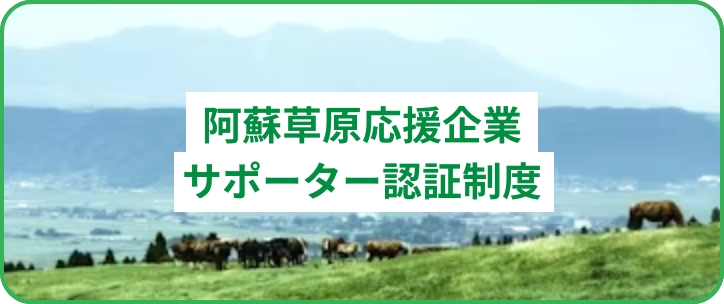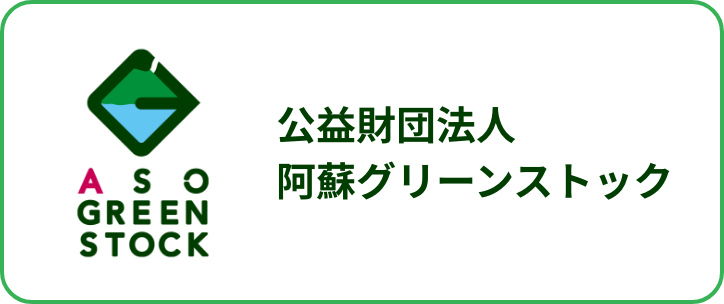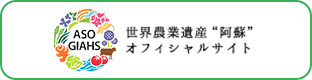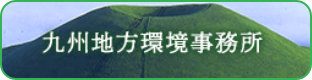「人間は、自分たちの首をかけた壮大な実験を行っています」
筑波大学山岳科学センター准教授の田中健太先生が警鐘を鳴らすのは、この100年で国土の10%を覆っていた草原が1%にまで急速に激減してしまった先に待つ、わたしたちの未来だ。数えきれない命に支えられている人類の生態系に、それがどのような影響を及ぼすのかは予測ができない状況で、わたしたちが今すべきこととは。
「幼い頃、長期休みのたびに長野県に滞在していた」というブランディングディレクター・行方ひさこさんと、長野県に拠点を構え、菅平高原・峰の原高原で草原の研究を続ける田中健太先生。互いに長野県にゆかりのあるおふたりのトークは、草原と災害の関係性から、“生物多様性”の重要性まで大いに盛り上がりをみせた。
縄文時代から続く草原を維持しているのはスキー場?!
田中 行方さんのファーストキャリアは、ファッションブランドの立ち上げだったそうですね。草原はファッションとも古来から関わっています。“むらさき”という植物は、むらさき色の語源なのではないかと思っている絶滅危惧種ですね。“茅”とはさまざまな種類の植物の総称ですが、中でも「苅安」は、染料のひとつとして活用されていました。見た目はススキのような植物ですが、驚くほどゆたかな色が出てくるんですよ。
行方 自分たちの手でしかものを生み出せなかった時代には、きっとそうした試みを繰り返しされていたのでしょうね。
田中 今でこそ流行の最先端は、新しい工業製品だと思いますが、少し前までは流行の最先端は生き物由来の何かだったと思います。草原は特に生き物の種類が多い場所なので、数々の流行を生み出してきたはずです。
行方 振り返ってみると幼い頃、ハンカチに挟んだ実を潰してみたり、食べてみたり。通学路を歩くほんのわずかな時間でも、さまざまな植物と触れ合った思い出があります。そういう小さな実験の中に、ものを生み出すヒントが隠れていますよね。田中先生は、長野県にお住まいでいらっしゃるそうですね。
田中 そうなんです。2013年から長野県で草原の研究と保全に取り組んでいます。
行方 わたしは母方の祖父母の家が長野県にあったので長期休みのたびに足を運んでいて、菅平には毎日のようにスキーをしに行ったりもしていました。
田中 そうだったんですね!スキー場って、わざわざ草原をつくってスキー場を作るわけではなくて、50年ほど前には日本の至るところにあった草原に、リフトをかけて整備されてきたんですね。つまり、縄文時代から続く草原を“スキー場”という存在が維持・管理しているわけです。
スキー場の周辺は今はすっかり森林化してしまったので、現在はスキー場だけが草原由来の生き物たちを守っている状況です。だからスキー場の雪の下には、実は絶滅危惧種が目白押しなんです。
行方 雪の下がそんなことになっていたとは‥。縄文時代から草原があったという事実にも驚きますね。
本来の自然は災害だらけ。人と災害が草原を育んできた
田中 よく森が大事だと言われますが、草原は放っておけば自然に森林化します。一般的には「森林の状態が自然な状態であり、守るべき存在だ」と思われがちですが、草原の方がずっと守るべき存在なんですね。というのも、日本で絶滅危惧種になっている生き物の3割〜4割が草原でしか生息できない生き物であり、草原の消失によって行き場を失った彼らの多くが絶滅危惧種とされているからです。
行方 “生物多様性”という言葉はこれからのキーワードのひとつだと思いますが、草原は生物多様性の宝庫なのですね。
田中 まさに草原は絶滅危惧種のホットスポットです。草原を守らないと本当に大量絶滅が起きてしまいますし、私たちの子どもや孫世代にゆたかな日本を残すことは到底できません。よく「森を守ろう」という呼びかけがありますが、保護の優先度の高さでいえば圧倒的に草原です。「草原に植林をしよう」とか、「森を伐ってはダメだ」と叫ばれていますが、生き物の豊かさを守る上では逆行するようなムーブメントも少なくありません。
行方 友人の実家が福島県にあるのですが、本当に森に飲み込まれるような勢いで森林化していると伺っています。草原に生きていた生き物は、森では生きていけないんでしょうか?
田中 元々、人間が草原をつくるようになる以前は、そうした生き物たちはどこにいたのかというとても重要な質問ですね。世界の中でも特に日本はその傾向が強いのですが“自然”の世界は本来、災害だらけだったんです。台風が来て森が倒れ、火がついて焼失し、川が洪水する。こういう災害が毎年のように起こるのが本来の自然です。それを人間がどんどん食い止めてきたという状況があります。今は、自然に草原ができるということがほとんどなくなってしまった。だからこそ、極端な草原減少が起きているんです。
利根川は放っておけば毎年のように流れを変えていて、毎年のように草原をつくり出していたと推定されます。そこを江戸時代の徳川幕府が大改修を試みたんですね。しかも東京湾に流し込んだら、江戸が荒れてしまうから、房総半島まで迂回路をつくり、堤防をつくり、洪水を鎮めて来た。そのことによって関東平野から草原がなくなり、絶滅危惧種の生き物が一気に増えたんです。
絶滅する生き物たちが、生態系に及ぼす影響は予測できない
行方 そもそもできるだけ多くの生き物が生き残った方がいいというのはなぜでしょうか。
田中 「生き物が多い方が生態系の機能が高いのはなぜか」「生き物が多いことがなぜ人間にとって良いのか」というテーマは、ここ20〜30年の間に常に注目を集めているトピックです。私たちが直接食べている作物が100種類としたときに、それを支える生き物がどれぐらいいるのか、ということは計り知れません。例えばトマトが 実をつけるためには、花蜂の存在が必要です。その花蜂の種類が多ければ多いほどトマトの実付きがよくなると言われています。それだけの花蜂を支えるためには、周辺にもっと多くの生き物がいて、ネットワークがあって、お互いを支え合っている。日常生活の中で想像以上に膨大な数の生き物に、直接的、間接的にお世話になっています。それを無自覚に絶滅させてしまうことによって、将来的には世界経済そのものが止まってしまう可能性がある、という大きな問題が生じているのが今ですね。次の世代に私たちと同じくらい安定的な世界を残していけるかどうかもわからない中で、生きものたちと共存が可能な経済体制に移行しないと、今後は経済発展も期待できない。そういう未来が間近に迫っているので、これまで経済発展を促していた金融や企業の人々が、むしろ積極的になんとか自然と並行する経済を作らなくてはと動き始めたのが、生物多様性におけるこれまでの大まかな流れです。

行方 ここ100年ほどの生き物の減少傾向からどのようなことが言えますか。
田中 生き物の減り具合で言えば、地球の歴史上かつて類を見ないほどです。目に見える生き物、つまり多細胞生物が生まれたのは、地球の46億年の歴史の中で言えば、わずか6億年ほどのこと。6億年の中でいえば、そのうち大量絶滅は5回。中でももっとも最近で有名なものが6400万年前。隕石が衝突するという宇宙規模の災害によって引き起こされた白亜紀の恐竜の絶滅です。その前に起きた地球史上最大の大量絶滅が起こったと言われているのが2億5000万年前。何千キロメートルという距離に渡って溶岩が流れ出る大噴火が起こり、地球の気候がガラリと変わってしまった結果、大量絶滅が起こったといわれています。
行方 まさに“天変地異”ですよね。
田中 ここ100年くらいで言われている絶滅の速度というのが、かつて天変地異が起きた速度よりもうんと速い。絶滅した生き物の数は過去の大量絶滅より少ないのですが、その速度は圧倒的。とんでもない速度で生き物がいなくなっている。それによって人間を支えている生態系がどうなるのかは、地球が今まで経験したことがないので誰にも予測がつかない部分です。人間は気軽に自分の首を賭けた大実験を無意識にやってしまっている。それが絶対にダメだという根拠が強くあるわけではないですが、今のままで大丈夫だという保証はまったくない状況だと思います。
行方 答えのない中でどのようなことに取り組めば状況は変えられるのでしょうか。
田中 身近な自然に付き合っていくことです。これまで自然災害によって自然の生態系は再生産されてきました。さまざまな技術を駆使して災害を止めてしまったために崩壊してしまった。そこで草原に生きて来た生物をなんとか後世に伝えるために、災害の代わりになることを人間が営みの中で続けて来たわけです。だからこそ、生き物たちの避難場所が守られていたんですが、ここ50年〜100年の間に人間のライフスタイルが変わってしまい、草原を利用する必要性がなくなってしまった。結果として人間のつくる草原も、災害によって生み出される草原も無くなってしまいました。そうした中で行き場を失った原野の生き物たちが急速に絶滅している。今、関東平野を災害だらけの原野にするなんて選択はできませんが、私たちが身近な自然に親しんだり、分け入ったりして、好きになったりして、自然に手を加えていくことができないか、という問いを僕はいつも考えています。行方さんは、今どちらにお住まいですか?
行方 都内です。
田中 都会でも川の土手や高圧電線の下などには、草原っぽい環境はまだ残っていると思います。そういう場所の草刈りに参加したり、草刈りがされていることを見守ったりすることは大事にしてほしいです。
これまで自然に関わって来た人たちの高齢化が進んでいます。里山は20年に1回伐採したら、その切り株から木が生えてきて、また20年後には、ちょうどいい太さの木がたくさんとれる。それを薪や炭にする暮らしを何百年も続けてきたら、生き物がとてもゆたかな森が生まれた。それはなぜかというと人間が環境を整備したことによって自然界に災害を無くしてしまったからです。草原と同じように里山にも自然災害が必要な生き物たちが逃げてきたからなんですよ。里山も草原も手を入れていくことが大事なのに、今は急速に放って置かれて困った状況にあるんですね。
行方 「自然は手をつけない方がいい」「草原に木を植えよう」という動きは、今にそぐわないものでもある、ということですよね‥。そうしたお話は、どこで知ることができるのでしょうか?

田中 研究者として現場での調査・研究と、発信の場をどのように設けていくかは課題です。ただ、一人ひとりにできることとしてどこにアンテナを張ればいいかというと、元々はどのような自然だったかに目を向けることです。ちょっと難しいですが森を見るにしても元々草原だった場所に植林した人工林なのか、天然林なのか、原生林なのか。性質を見極める視点を持つことです。
もう一つは、その土地の郷土食のようなものに目を向けることですね。文化やファッションにも共通すると思うのですが、ワインなども単なるおいしさに目を向けるのではなく、その土地でしか作れない個性があるかどうかを評価する。生き物の多様性も同じで、そこにしかいない生きものに対する優先度がもっとも高くなりますし、同じ種類のものでもその地域にしかいないような個性のある集団というのは守るべき対象であると思います。
土地の個性を味わうワインのように森の多様性を見る
行方 なぜ、草原より森の方がプライオリティが高いと認識されてしまったのでしょうか。
田中 江戸時代の中期に一度、森が少なくなってきたという時期があるんです。江戸〜明治時代頃までは日本の国土の10%は草原で、草原があることが当たり前の時代がありました。そこで、森林は守るべき存在だと刷り込まれてしまったんでしょう。そこから社会は驚くほど変化したけれど、森林に対する見方は刷新されず今はむしろ森林飽和の状態。実は現代ほど国土に森林が多かった時代はないんです。一方で原生林はとてつもなく大事で、もちろん絶対に守らなければならないものですが、50年前は草原だったという若い森はありふれている。要するに“森林”の中身が重要です。今ある森林の半分は人口林で、残りの半分は天然林。そこに原生林と呼ばれるものはほとんどない状態。この状況で若い森が大事かといえばそうではない。絶滅危惧種を復活させるためには、以前草原だった場所にある若い森はむしろ伐った方がいいんです。
行方 森林の質を推し量ることは、一定の知識がないと難しいかもしれませんが、ワインを味わうようにその地域の食やものづくりと紐付けて考えることからできることを探すことはできますね。
田中「歴史にないものを今日からこれが郷土食です」と言ってもあまり魅力がないでしょう。天然の生きものの絶滅の仕方も著しいですが、人間が品種改良してきた作物や家畜の品種のなくなり方は、比べ物にならないくらいの速度で消えています。
行方 郷土食とは、土地の個性と色濃く結びついているものですよね。
田中 それと同じで絶滅危惧種というものは、限られた場所にしか存在しない。その地域で守るしかないものです。固有種もその地域にしかいない。だからこそ“郷土食のような特色”に注目することが大事です。どこでも同じような“自然”ではなく、それぞれの地域の人たちが「ここが自分にとって帰るべき場所だ」と思えるような状態を保つことに価値がある。それを取り戻す1番の近道が“草原再生”なんです。
行方 歴史に培われているからこそ大事なものであり、そこに個性が宿る。今のわたし自身のライフワークとも重なる、とても深い学びの時間でした。森にまつわる誤解も解けました。今日は本当にありがとうございました。
【草原ライターのあとがき】
どうやらわたしは、これまで草原の成り立ちにとって重要な2つのことを知らずに生きてきてしまったらしい。ひとつめは、人間とともに草原の維持管理を担う存在が自然災害であったこと。ふたつめは、森に対する見方についてだ。
10万年もの間、日本列島で草原の再生を繰り返し、人間にとって住みよいゆたかな世界を育んでくれたのは、近年わたしたちが胸を傷めている“自然災害”だった。
大地震、火山の噴火、飢饉、鉄砲水など、災害に見舞われながら、草原はその土地なりのゆたかな生態系を培ってきた。そこで進化した人間は、災害を防いだり、防ぎきれなかったりしながら、自然との共存のバランスを保ってきたのだ。
“森”とひとことで括るのではなく、人工林、天然林、原生林を見極める眼を持つこと。歩く速度の登山をすればそのグラデーションが明確にわかる。たどり着いた先のブナの樹々が佇む原生林は、言葉を失うほど美しい。一方で林業の世界では「自然は手付かずの方がいい」という誤った認識の蔓延によって、“守られてきたはずの森”は、放置された結果、荒れた森と化していた。そんな森が飽和状態にあるのが、日本の森の実情だ。
ふとこれは、子育てと重なるかもしれないと思う。
なんでも与えるだけでも、放置していてもいけない。
いつまでも親のいうことばかりは聞いてはくれないし、
お利口さんなだけでもいられない。
過剰にコントロールしようとしてはいなかったか?
見過ごしていたことはなかったか?と自問自答する。
結局は日頃から相手をよく観察し、些細な変化に気づくことが1番の近道だ。
そのたゆまぬ繰り返しが、ゆたかな関係性を育む。
調和のとれた“循環型社会”は、自分のなかにある誤解に気づくことからはじまる。
地球のこと、草原のこと、今を生きる私たちのこと。
それは遡っていけば奇跡のような連なりのなかにある(ちなみに、奇跡とは“確固たる強い意志”が起こすものらしい)。
その奇跡のような世界を次世代につなげられるかどうかはまた、今を生きる私たちにかかっている。
※こちらのインタビューは2024年に取材させていただいた内容をもとに編集いたしました。

【Profile】
田中健太(たなかけんた)
1974年福岡県生まれ。筑波大学山岳科学センター准教授。根子岳・四阿山保全協議会。マレーシア熱帯雨林の研究で京都大学博士号。2013年から草原の研究と保全を本格的にスタート
行方ひさこ(なめかたひさこ)
アパレルブランドの経営、ファッション、ライフスタイルブランドのディレクターとして活動。近年では、食と工芸・地域活性などエシカル&ローカルをテーマに、昔からの循環を大切に繋げていきたいという想いから、その土地の風土や文化に色濃く影響を受けた「モノやコト」の背景やストーリーを読み解き、自分の五感で編集すべく日本各地の現場を訪れることをライフワークとしている。2021年より地域の文化と観光が共生することを目的とした文化庁文化観光推進事業支援にコーチとして携わる。国内外の工芸品やアートをキュレーションした企画展「ARTS& CRAFTS」が伊勢丹新宿店で不定期開催中。
[Interview]
草原ライター
中城 明日香 (なかじょうあすか)
島と草原の文化をこよなく愛する編集者・ライター。都市と田舎のどちらにも心を動かし、五感で感じたことを言葉にする。だいたいゴキゲン、好奇心だけはいつも旺盛